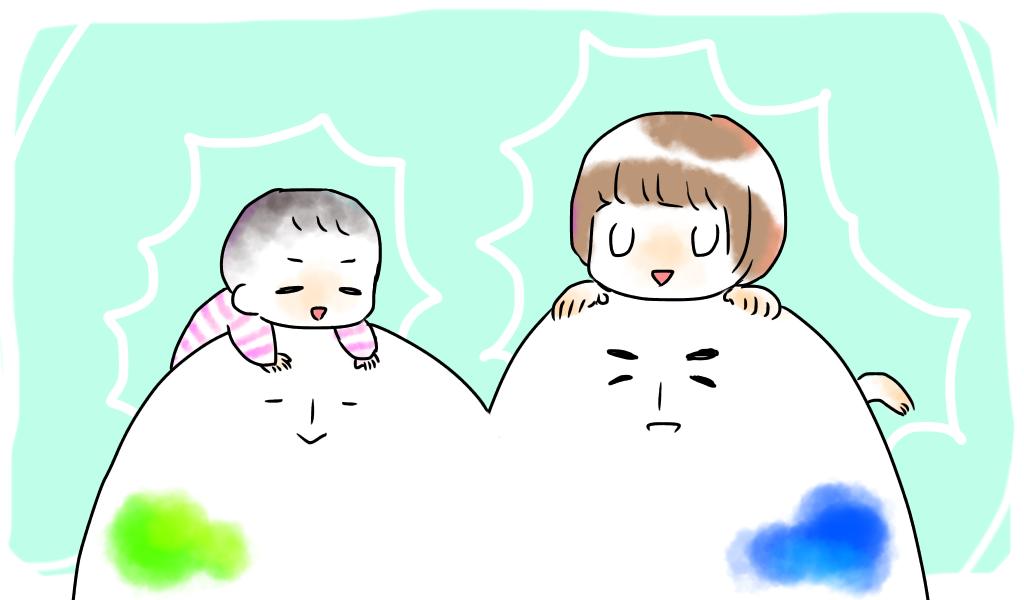
こんにちは、のいです。
普段は「こめうまベイビー!」という育児日記的なものをのんびりと書いています。
赤ちゃんと触れ合ったことがあまりなく、抱っこすらよく分からなかった私も母親歴2年目。2歳の長女、そして今年3月に生まれたばかりの次女がいる我が家は毎日にぎやかです。
さて、私は長女を妊娠してから今までさまざまな育児グッズを買い揃え、使ってきました。けれど、それが自分や我が子に合うかどうかって、やっぱり使ってみなければ分からないんですよね。「うっわ便利!」というものがあれば「これはちょっと使いこなせないな……」というものもありました。
そこで今回は、長女の体験をもとに私が実際に使ってみて「便利!」「これはいい!」と思ったものを、娘の成長を振り返りながら紹介したいと思います。子育て中の方やこれからお子さんが生まれる方にとって参考の一つになれば嬉しいです。
完全母乳派の味方! レンチンで手軽に消毒
長女を妊娠していたときのこと。必要なものを揃えていく中で悩んだのが「哺乳瓶の消毒をどうするか」です。
というのも、私は母乳の出さえ良ければ母乳で育てたいと考えていたので、あまり哺乳瓶を使わないんじゃないかと思ったんですよね。そうなると、真っ先に思い浮かんだミルトンのような薬液だと容器がちょっと大きくて邪魔に感じてしまうかもな……と。
夫婦2人にはゆとりがあるこの賃貸アパートも子どもが増えると物も一気に増える……。哺乳瓶の消毒は必須だけど、できるだけ場所を取りたくない……。かといって鍋で煮沸消毒するのはちょっと面倒だし危ない……。
と、悩んだ末に購入したのが、哺乳瓶1個分を消毒できる「レック Dream Collection 電子レンジ用ほ乳びん消毒器」です。

【楽天市場】 レック Dream Collection 電子レンジ用ほ乳びん消毒器の検索結果
1日1回の使用にぴったりのサイズ。サブ利用にもGOOD
何といっても、私にとって一番うれしかったポイントはサイズです。結局ほぼ母乳だったので、哺乳瓶は使っても1日1回程度。そのため、この哺乳瓶1個分がスポッと入るサイズが、抜群にちょうど良かったです! 哺乳瓶ケースにもなるから、保管時も場所を取らずコンパクトコンパクト。
ただ、もし哺乳瓶を使う頻度が高いのであれば薬液の方が便利かなとは思います。薬液だったら数本の哺乳瓶を一度に消毒できるし、洗った後は薬液に浸けておくだけ。なのでミルクで忙しいママには薬液の方がいいかもしれません。
とはいえ、この哺乳瓶消毒器はこれはこれで帰省時や旅行先に持っていけるので、サブとして購入して損はないかなと。
使い方も簡単。容器に指定の量の水を入れ、そこに洗った哺乳瓶を置いてフタを閉めたら、電子レンジで3分。たったこれだけで完了です。
※チンしたてはアツアツなのでご注意を
さらにはこのケースで離乳食用の蒸しパンも作れちゃうから、長く使うことができます。

と、とても便利なアイテムを手に入れたわけですが、長女は哺乳瓶を嫌がったので大変でした……。
友達の結婚式に参加するため、ミルクが飲めるよう事前に慣らしていたつもりが当日は大変なことに。なんてこった。別の私の不在日にはラスト授乳から6、7時間近くミルクを飲まない拒否っぷり(最終的にスプーンでやっと飲んだらしいですけど)。夫よ……すまん。
で、そんな長女も卒乳。今は次女に絶賛授乳中です。次女が新生児の時は、胸がカッチカチに張り過ぎて痛いわ上手く飲んでくれないわで度々搾乳して飲ませていましたが、それも落ち着いて現在は平穏な日々を過ごしています。
今のところミルクも飲んでくれますが、いつ長女の二の舞になるやら。完全拒否にならないことを祈ります。
慎重かつズボラなので小分け冷凍しまくる
母乳をごくごく飲みまくっていた長女も生後6か月頃から離乳食デビュー。
10倍がゆの裏ごし小さじ1から始まる離乳食は、一度にあげる量が少ない上にいちいち裏ごししたりすり潰したりするのが面倒です。そこで私はよくまとめて作って冷凍していました。
その時に使用したのが、ラップ、フリーザーバッグ、そして離乳食用の小分け冷凍トレー「リッチェル わけわけフリージングブロックトレー」です。

冷凍保存三種の神器 その1「ラップ」
ラップは液体状じゃなければ何でも包めるので、少量のしらすを分けるのも一食分のおかゆや野菜の煮込みを分けるのも自在。少量ずつ分けるなら小さいサイズのラップが使いやすいです。
冷凍保存三種の神器 その2「フリーザーバッグ」
かぼちゃやいものペーストにはフリーザーバッグを使用。ペーストをフリーザーバッグに入れたら、平らにして箸で真っ直ぐ線を引くように筋を入れます。そうすると凍った後にポキポキと割るようにして適量を取り出せるんですよね。
ちなみに黒くなりやすいバナナはフリーザーバッグに一本そのまま入れ、袋の上から潰し、空気を抜いて冷凍すると黒くなりません。あとは欲しい量だけポキッと取り出してチンするだけ!
冷凍保存三種の神器 その3「わけわけフリージングブロックトレー」
と、このようにラップもフリーザーバッグもとても便利で、これだけで何とかなるっちゃなるんですが、離乳食づくりにおいては「わけわけフリージングブロックトレー」が本当に重宝しました。
【楽天市場】 リッチェル わけわけフリージングブロックトレーの検索結果
特に何でもすり潰す「ゴックン期(5、6か月頃)」の離乳食と、細かく刻む「モグモグ期(7、8か月頃)」の離乳食で大活躍。私は15ml×12ブロックのものを使用していました。
とあるレシピ本によるとゴックン期後半の離乳食は、10倍がゆ40g、絹ごし豆腐20g、かぼちゃ10g、ほうれん草の葉5g……とのこと。雑な主婦だから普段の料理は目分量ですけど、赤ちゃんのこととなると何かあっては怖いので、私もこういったレシピに沿ってきちんと量っていました。でも毎食量っていると手間です。
なので、おかゆや野菜のすりおろしをまとめて作り、それを〇gずつ量ってこのトレーで小分け保存するというわけです。また、だしを流し込んでだしキューブを作っておけば、味付けやスープにちょこちょこっと使える! 凍ったらフリーザーバッグに移して保存するとその都度取り出しやすいです。
もちろん百均などで製氷皿を買ってもいいんですけど、このトレーは柔らかいので底を少し押せばぽこっと取れるのが便利でした。製氷皿ってなかなか中身が取り出せなくて地味に苦労するんですよね……。
ただし無理矢理ねじったり強く押し込んだりすると割れることがあるそうなので、それだけは注意。
ぽこぽこ出してチン! 「スピード野菜がゆ」

私がよく作っていたのは「スピード野菜がゆ」です。おかゆのブロック(15g)×3つ、にんじんのブロック(5g)×1つ、ほうれん草のブロック(5g)×1つをお皿に入れ、そこに水を少し振りかけてラップをしたら電子レンジで1分30秒~2分ほど加熱。離乳食は量が少ないから加熱時間も短く、たったの数分で完成です!
離乳食ってたくさん食べてもらうためにもご機嫌なうちに食べさせられるといいのですが、いちいちキッチンに立っているとぐずっちゃうことがあるんですよね。また、私自身が疲れて作る元気がないときもある……。そういうときにすぐ用意できるのって最高に楽でいいです。
楽ちんといえばベビーフードもそうですね。私は「今日はストックがない! 食材もない!」ってときや出先用に常備してました。まとめて作る方が面倒という人もいるでしょうし、やっていくうちに自分のペースを見つけられたらいいですね。
ゆっくりトレーニングでお箸デビュー
離乳食が進んで手づかみ食べを覚えた長女。さらに1歳3か月頃にはフォークやスプーンを自分で持って使えるようになりました。
そうなると次はお箸!
長女は大人がお箸を使う様子を見て触りたがっていたので、フォークやスプーンと一緒にベビー用のお箸をテーブルに置くようにしていました。それが「エジソンのお箸」です。使ったことがある、使っているという人も多いのではないでしょうか。
これは2本の箸がくっついていて、輪っかに指を通せばきちんとした持ち方で箸が持てるというもの。しつこく持たせてお箸が嫌いになったら困るので、興味を持ったときに持たせる程度にゆるーく教えていました。

すると次第に上達していき、自分でお箸の輪っかに指を入れて持てるように!
初めはお箸の上にご飯を乗せて口に運んでいましたが、いつの間にか箸先を開いて食べ物を掴んで食べられるようになりました。

このお箸は先が膨らんでいて滑り止めもついているため、食べ物を掴みやすくなっているようです。お豆も器用に掴んで口に入れるのね。
次に試したいお箸は?
来年には幼稚園に入る長女。果たしてそれまでに普通の箸も扱えるようになるのか。
まずは幼児用の短いお箸を買うことから始めようと思っており、「何が良いかな」と探して今一番気になっているのが「イシダ 子供用三点支持箸」。
指の形に沿ったくぼみがあり、ポイントにイラストが描かれているので子どもでも分かりやすいのだそう。日本製で安心!
次のステップアップに丁度良さそうなものを見つけられたけど、あとは本人が気に入るかですね。……気に入ってくれるといいなあ。
**
育児って大変ですね。でも楽しいですね。
初めての育児で右も左も分からない中、泣いてばかりだった長女ももう2歳。舌足らずで「かーしゃん」と笑って呼んでくれるのが嬉しくて、日々言葉が増え、できることが増えていく様子に驚いてばかりです。
うまくいかなくてイライラしたり辛くなったりもするけど、我が子はやっぱり可愛い。より我が子を可愛がるためにも楽できるところは楽して、便利なものは活用してほどほどに頑張ろう、そう思う私なのでした。
今回は私のお気に入りアイテムをご紹介しましたが、少しでもお母さんお父さんたちのお役に立てましたら幸いです。



