
「ののか、カメラ欲しくない?」
ある日突然、父から電話があった。電話を受け取った先は、当時住んでいた綾瀬のアパート。平日の昼間にも関わらず、パジャマを着て横になっていた。
わたしは当時、休職をしていた。
新卒1年目で入った会社は秋くらいから段々と行けなくなった。完璧に準備をして玄関に向かうのに、靴が履けない。じっとりと汗をかいて、息が深くなる。気づけば、始業時刻に間に合うか間に合わないかの時間になっていて、そのころになってようやく、会社に休む連絡をする。
会社を休んでも楽になるわけではなく、コンビニに行くだけで人の視線が気になった。
―― 平日の真昼間に出歩いているわたしは、どんな風に見えているんだろう。
そう思うと、世の中すべてに無価値と言われているような気がして、平日の昼間はまともに外を歩けなくなった。夜は夜で眠れなくなり、幻聴が聴こえる。知らない声が「死ね」と言う。あのころ、世の中全部が歪んで見えていた。

そんな折、父から電話がかかってきたのだ。
父は自宅の前に置いたプレハブを事務所にして、事務機器を売ることを生業としている。いつも温厚で、怒られた記憶があるのは3歳くらいのときに本を踏んで遊んでいたときくらい。
多分、世間一般の親子と比べて仲は良いほうだと思う。それでも電話なんかするのは、パソコンの調子が悪いときに直し方を聞くくらいで、父のほうから電話をかけてくることなんて、まずなかった。
それなのに「カメラ」だ。しかも、よりによって一眼レフ。特段欲しいと言った記憶もない。ちょっとした写真ならiPhoneで間に合うし、コンデジだって持っている。どうして急に、カメラなんだろう。
不思議に思いながらも「もらえるなら、欲しいかも」とだけ言った。どうせ昼間は家から出られず退屈なのだ。けど、新しいカメラがあったら、1日の進み方がもう少しだけ早くなるかもしれない。
そうしてわたしが年末に帰省したとき、手渡されたのがCanonのKissだった。
「ののかは赤が好きだから」
そう言われて箱を開けてみると、ボディがワインレッドの一眼レフが出てきた。確かにわたしは赤が好きだった。中学校のころは赤が好きすぎて、自室の壁に赤い色画用紙を敷き詰めて、イっちゃってる人の部屋みたいにしたこともある。
そんなことを思い出しながら、わたしは「ありがとう」と言って、伏目がちにカメラをいじった。社会人になったら、両親に旅行をプレゼントしようなんて思っていたのに、結局わたしは休職中で、父親からカメラをプレゼントされている。それが何だかやるせなかったのだ。カメラはコンデジやiPhoneよりもずっしりとしていて、はるかに重かった。
カメラを触っている間じゅうずっと、父はニコニコしてわたしのことを見ていた。目を合わせているわけではないが、わかる。
「たくさん撮るといいよ」
ニコニコしたまま、父はそう言って、「来年も頑張って働くぞ」などと続けた。わたしはますます、父がカメラを買ってくれた理由を知りたくなった。
どうして急に一眼レフを買ってくれたんだろう。ネットで安いものでも、新品なら5万円はカタい。いつもなら、父が無駄な買い物をしたときに糾弾する母も、ニコニコして見ていた。不思議に思ったけれど、何だか気恥ずかしくて理由を聞けなかった。
*

そうして年が明け、わたしはカメラを携えて東京に戻り、毎日1枚は写真を撮ろうと決めて、退職することになる5月まで毎日欠かさずシャッターを切り続けた。
撮った写真は、言葉に添える形でブログにあげた。反応があった。すごくあった。1度会ったきり、SNS上でだけで繋がっていた人から連絡が来てまた会うことになった。「ののかちゃん、面白いよ」と賞賛してもらった。社会人になってから褒められたことなんてほとんどなかったから、夢みたいな時間だった。
やがて、調べものをして家で記事を書く仕事をもらえるようになった。半月後には取材案件の話をいただいた。単価は調べもの記事の倍額だった。ただ、担当者の方には1つ懸念点があったみたいだった。
「写真がけっこう大事なんだけど、ののかちゃん良いカメラ持ってる? 一眼レフとか」
ワインレッドカラーが頭の中に満ちていく。
「あります!」
わたしは被せ気味に答えた。
「写真、撮れる?」
「撮れます! うまく撮れるかわからないですけど、半年くらい毎日触ってたので恐らく!」
こうしてkissは、わたしの相棒になった。それ以降も「写真が撮れる」という理由でお仕事をたくさんもらえて、わたしは少しずつ自信を取り戻していた。気づけば体調も嘘みたいに良くなっていた。
**

そんなある日、いつものように母と電話で他愛もない話をしていたときのこと。「最近、一眼レフを持っているから、ってお仕事をたくさんもらえるようになってね」と話すと、母がしばらく黙って、
「ののか、お父さんがどうしてカメラを買ってくれたか、聞いてる?」
と言った。
「ううん、聞いてない」
そう言うと、電話越しで母が話し始めた。
「お父さんね、ののかが死ぬと思ったんだって」
えっ、と言葉を飲んだ。確かにわたしは何度か発作を起こして救急車を呼んだり、いのちの電話にダイヤルしたりしていた。帰省中、実家のある北海道のマイナス20度の銀世界の中でお酒を飲んで、そのまま眠ってしまおうと何度も考えた。でも、そんなこと、父には言っていなかった。母は続ける。
「お母さんもそんなに高いカメラ買い与えてどうするの? って言ったの。でもねお父さん、“俺、後悔したくないんだ”って言ったの。ののかがもし万が一死んじゃったときに後悔したくないって。綺麗なものを見る癖がついたら、自然と心が穏やかになるかもしれないって言ってたんだよ」
「後悔したくない」というのは、父がいつも口にしていた言葉だった。

その年、父は実母を亡くしていた。親思いの父は、車で1時間以上離れたところに住んでいた(わたしの)おばあちゃんの家に2日に1度は通って、様子を見に行っていた。住み慣れた家を離れたくないというのは、おばあちゃんの希望。仕事の合間とはいえ、甲斐甲斐しく世話を焼く父を見て、母は何度も「近くに引っ越してきてもらえばいいのに」と言ったけど、その度に父は「俺、後悔したくないんだ」と言っていた。
父にしてみたら、春先に実母を失ったばかりなのに、今度は娘が年末に今にも死にそうな顔をして引き揚げてくるという状況だったのだ。親不孝なことをしてしまったなと思った。
お正月休みの後、「年が明けても実家にいると、人の目が気になるから東京に戻るよ」と言うわたしに「東京に戻すのが心配だ」と母は言ってくれた。きっと父も同じ気持ちだったはずだ。だけど、父は背中を押してくれた。
「ののかの好きにしたらいい」
それで、せめてもの一眼レフカメラ、だったのだ。実家にいなさいとは言いたくない、だけど、付いていくわけにもいかない。そんな親心が、“父がくれたkiss”には込められていたのだ。
母の話を聞きながら、わたしはカバンの中に入っていたカメラを握りしめて、涙をこらえた。
ちょっと照れくさいなと思ったワインレッドカラーですら愛おしかった。
―― お父さんごめんね、ありがとう。
結局、電話を切った後、堪えきれずにわたしは泣いてしまった。涙越しに見えるkissは日の光を受けて、いつまでもキラキラと輝いていた。
***
朝起きて取材に向かう準備をする。メモ帳にペン、ノートPC、ICレコーダーに、一眼レフを入れて、リュックは今にもはち切れそうにパンパンになる。
iPhoneみたいに、ミラーレスカメラみたいに軽くない。ずっしりとリュックを重くするkissを背負って、一歩一歩、一日一日を生きていく。

【楽天市場】 canon kissの検索結果
【楽天市場】 一眼レフカメラの検索結果
§§§
あのころのこと、父に聞いてみた

母からは父の気持ちを聞いたけど、父と直接はカメラの話をしていない。
「お父さんが買ってくれたカメラのおかげで仕事がたくさんもらえるようになったよ」
「よかったね、頑張ってね」
のやりとりくらいだ。父とは本当に仲が良いのだが、やはり先のカメラの話はどうにも気恥ずかしくて、できない。
しかし今回、担当の方からの提案があったこともあり、遠く離れた北の大地に住む父に電話でインタビューをしてみることにした。以下、会話調でお届けしたい。
ののか:「もしもしお父さん、突然ごめんね。前に買ってもらったカメラのことなんだけど、あれってどうして買ってくれたか、覚えてる?」
父:「あぁ、カメラね。何だったかなぁ……。もう2年も前のことだから忘れちゃったなぁ」
ののか:「えぇっ、忘れたの!?(笑)そこを何とか思い出してよ!」
父:「最近もの忘れが激しくてさ(笑)。あぁ、思い出した!」
ののか:「え、なになに?」
父:「見たままの世界を撮れるカメラをプレゼントしたかったんだよ」

ののか:「見たままの世界を撮れるカメラ……?」
父:「うん。ののかがコンデジを持っているのも知っていたし、iPhoneでもそこそこ良い写真は撮れると思ったんだけど、多少画像が荒くなったり、歪んだりしちゃうでしょ? 辛い時期だったからこそ、コンデジやミラーレスみたいに液晶を通さず、ファインダー越しに目に映ったままを写せるカメラをあげたかったんだ」
ののか:「そうなんだ……」
父:「あぁ、あとね、撮った写真を通じて自分自身を見つめなおす機会にもしてほしいなと思ったんだと思うな。自分が“良い”と思った瞬間を切り取って、後から見直すことで自分自身を知ることにも繋がると思ったから」
ののか:「そっか、ありがとう」
父:「まぁ記事にするんだと思うから、あとは脚色なり何なりうまく書いてよ。それじゃあ仕事頑張ってね」
そう言って電話を切り、感傷に浸っていると、「また違う理由を思い出した!」と父から何度も電話がかかってきた。その理由は回を重ねるごとにどうでもいいものになっていき、最終的には「何となく」というところまでレベルが下がった。
ちょっと、お父さん。
そんな“父がくれたkiss”を携え、わたしは今日も取材に行ってきます。
著者:佐々木ののか
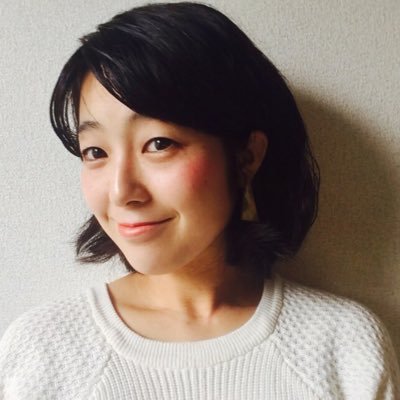
1990年北海道生まれのライター・文筆家。 新卒で入社したメーカーを1年で退職し、現在に至る。自分の経験をベースにした共感性の高いエッセイを書くのが得意。
Twitter:佐々木ののか | Nonoka Sasaki (@sasakinonoka) / Twitter
note: 佐々木ののか|note
